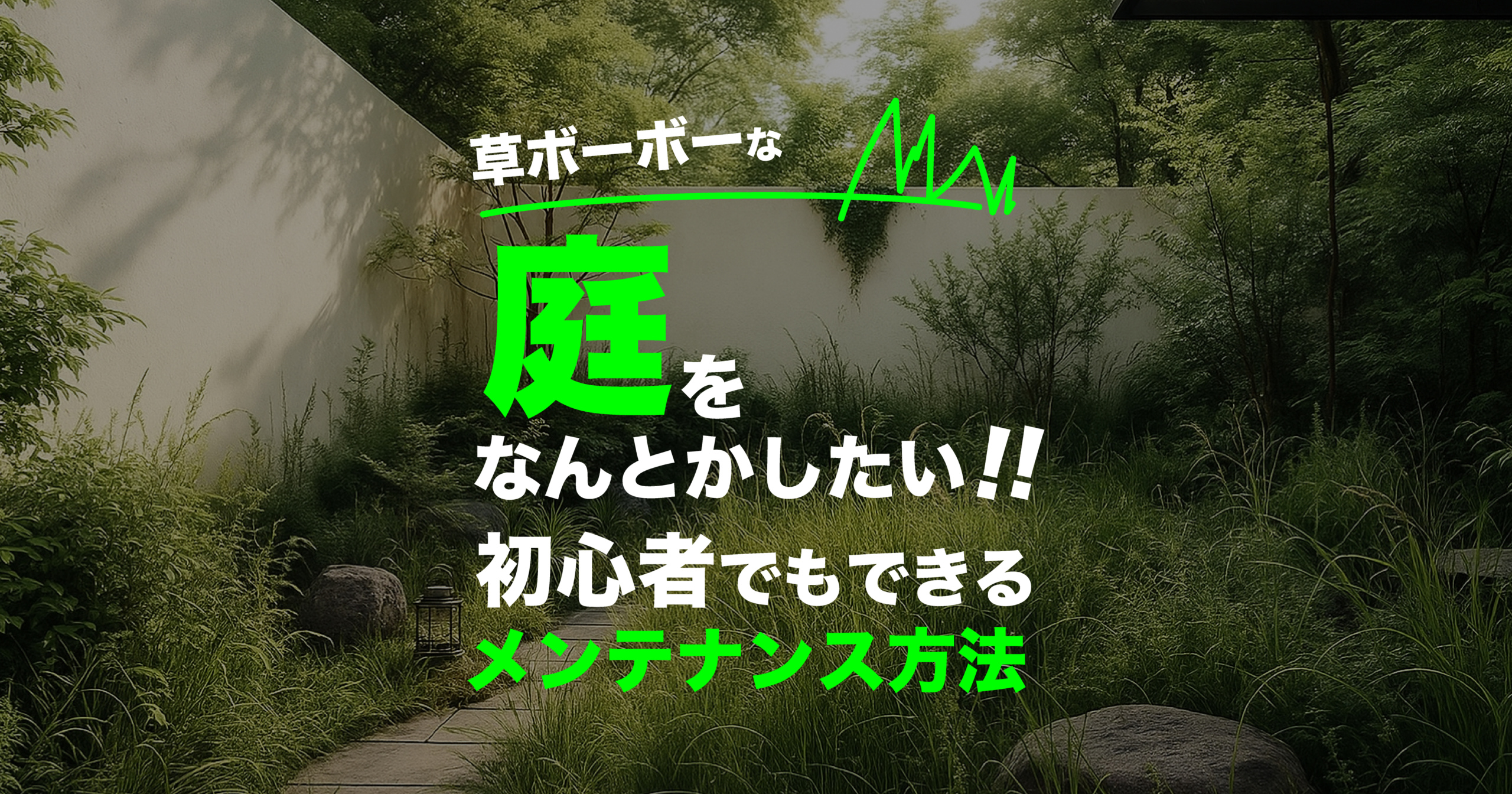「庭をきれいにしたいけれど、何から手をつければいいのかわからない…」
「雑草が生い茂ってしまい、手がつけられない…」
こうした悩みは、多くの方が共感できるものではないでしょうか。
庭というのは、時とともに変化し、手を入れなければ荒れがちになります。
しかし、正しい方法とタイミングを知っておけば、無理なく、
むしろ楽しみながら庭を美しく保つことは可能です。
本記事では、庭のお手入れの基本から、
季節ごとの具体的ケア、手間を抑える工夫、そしてプロに頼む選択肢までを網羅的に解説します。
初めての方でも取り組みやすく、かつ庭に愛着を持てるように意識して書きました。
まずは、庭のお手入れの「型(基本)」を押さえておきましょう。
1. 庭の手入れの基本とは?――大枠をつかむ

庭作業をやみくもに始めると、作業の無駄が増えたり、
見た目がバラバラになったりします。
まずは「庭を維持するために必ずやるべき作業」を体系化しておきましょう。
以下の項目が、庭手入れの基本構成要素です。
① 雑草の除去・防除
雑草は「自然の侵入者」であり、庭の見た目を乱すだけでなく、他の植物との水・栄養の競合、さらには害虫の温床になることもあります。庭ケアにおいて雑草は正面から取り組むべき課題です。
雑草除去のポイント
- 雨上がり直後がねらい目
土がやわらかくなっており、根ごと抜きやすくなります。 - 根までしっかり取り除く
雑草の根を残すと、すぐに再生します。とくに多年草(スギナ、ドクダミなど)は根茎を残さないよう意識を持ちましょう。 - 道具の活用
手で抜く以外に、「ねじりがま」「草抜きフォーク」「小型スコップ」などを使うと、根まで掘りやすくなります。 - 除草シートやマルチングの利用
防草シート、黒マルチ、ウッドチップ、バークチップなどを敷くことで、地表の光を遮り、発芽を抑制できます。 - 除草剤の選定
もし使用するなら、周囲植物に影響を及ぼさないものを選び、部分散布にとどめるのが無難です。
② 樹木・植物の剪定と整形
植物は放任すると暴れて乱れます。適度な剪定と形の調整が、庭を美しく保ち、植物自身を健康に育てる鍵になります。
剪定の基本ガイド
- 枯れ枝・弱った枝の除去
風通しや日当たりを良くするため、枯れた枝や込み合った枝を取り除きます。 - 花が終わった後の剪定
花後の剪定(切り戻し)は、翌年の花つきを良くすることにつながります。 - 樹形のバランスを意識して切る
不要な徒長枝はカットし、全体の形を整えて、庭にメリハリを与えましょう。 - 剪定時のタイミング
落葉樹、常緑樹、バラやつる植物など、種類ごとに適期があります。間違った時期に剪定すると、花の咲き方が変わったり、樹勢を弱めたりする可能性があります。 - 高木の扱い
高木は自力での剪定が難しく、誤ると危険を伴います。高所作業や大きな木は、プロに頼むことも視野に入れておきましょう。実際、小田急くらしサポートでは 「庭木の剪定・植栽管理」サービス を提供しており、見た目を整え、ゴミ処理まで含めて対応してくれます。
③ 土壌・地盤のメンテナンス
植物を支える「土」が健康でないと、どれだけ水をやっても栄養を補っても、生育が悪化します。庭を育てる上で土を整えておくことは不可欠です。
土づくりのポイント
- 腐葉土・堆肥の混入
定期的に腐葉土や堆肥を混ぜ込み、微生物の活動を活性化させ、保水性・通気性・肥沃性を向上させます。 - 水はけ改善
湿りすぎる場所には、砂、パーライト、軽石、川砂などを混ぜ、排水性を改善します。 - pH調整
植物によって好みの土壌pHは異なります。酸性傾向なら石灰を、アルカリ性ならピートモス等を混ぜて調整しましょう。 - 表土の交換や補充
長年使い込んだ土は疲れやすく、表面の栄養が消耗するため、良質な土を上から薄く重ねて補う「土壌リフレッシュ作業」も時折行うと効果的です。
④ 花壇・芝生・グランドカバーのケア
庭の顔となる花壇・芝生・地被植物(グランドカバー)は、定期管理が見栄えを左右します。
花壇管理
- 雑草抜きの徹底
花の株元に生える雑草は、できるだけ早めに抜くこと。 - 株分け・植え替え
株が大きくなった植物は、適期に分割や植え替えを行い、株の更新を。 - 追肥や液肥の活用
成長期には適量追肥、液体肥料を使って花を長く咲かせる工夫を。
芝生管理
- 定期的な刈り込み
芝は通常、1〜2週間に1回が目安ですが、気温や成長速度によって変動します。 - エアレーション(通気処理)
芝の根の呼吸を助け、硬くなった土に空気と水を通すため、穴あけ処理を年1〜2回行うと理想的です。 - 目土入れ
芝の隙間を補填するため、芝用の細かい土を撒く「目土」を使うことで、均一な密度を保てます。 - 芝の縁取り・エッジング
芝と花壇や通路の境界を明確にし、見た目を整えることもポイントです。
2. 季節ごとの庭の手入れポイント

庭仕事は「やることが一定」ではなく、「季節に応じて変わるタスクをリズムよく回す」ことが重要です。ここでは、月ごとの代表的作業も交えつつ、春~冬のケアを詳述します。
春(3月〜5月):芽吹きと準備の季節
春は、冬の間に止まっていた植物が一気に動き始める時期。痛んだ枝や古い落葉を掃き、庭全体をリセットしましょう。
主な作業リスト
- 枯葉・ゴミの清掃
- 雑草の初期除去
- 土を耕して肥料や堆肥を混ぜ込む
- 春咲き球根(チューリップ、水仙、スイセンなど)の植え付け
- 芝のエアレーション
- 新しく植える植物の選定と準備
- 支柱や支えの設置
- 春先の害虫・病害チェック(新芽が出る前に駆除が効きやすい)
春は「種まき」「植え付け」「整地」の好機です。ここで元気な土壌と適切な環境を整えておくと、夏以降の管理がぐっと楽になります。
夏(6月〜8月):勢いをコントロールする季節
夏は成長が最も活発な時期であり、同時に雑草・害虫・病気の拡大も起こりやすくなります。こまめなチェックと手入れが肝心です。
主な作業リスト
- 雑草の頻繁な除去
- 水やり(朝・夕方)
- マルチングで地温上昇を抑える
- 害虫チェック(アブラムシ、ハダニ、コガネムシなど)
- 病害チェック(うどんこ病、葉かび病など)
- 枝の風通しを意識して剪定
- 夏花壇の管理(切り戻し、追肥、花がら摘み)
- 強い日差しを遮る遮光や日除け設置
⚠ 注意点
- 真昼の作業は避け、早朝または夕方に行う
- 多湿・高温で病害虫リスクが高まるので風通しを意識
- 水やりの頻度・量は、植物の種類・用土・当日の気候によって調整
夏は「制御と予防」の季節です。手をかけすぎず、しかし無視してはいけない時期でもあります。
秋(9月〜11月):整理と蓄積の季節
秋は、夏の疲れを整えつつ、冬に向けて準備しておくべき期間です。落葉の処理や剪定、球根の植え込みなど、次の春につながる作業を中心に進めましょう。
主な作業リスト
- 落ち葉の清掃・集積・堆肥化
- 枝葉の処分
- 樹木・低木の剪定(ただし種類により剪定適期は異なる)
- 冬芽を傷めないような剪定を意識
- 球根植物(チューリップ、ヒヤシンス、クロッカスなど)の植え込み
- 耐寒性植物の準備
- 冬支度(根元のマルチング、寒冷紗・覆い対策)
- 病害チェックと葉の取り込み・処理
この時期にしっかり庭を整理しておくと、冬~春時期のトラブルをぐっと軽くできます。
冬(12月〜2月):休息と準備の季節
冬は庭全体にゆとりが訪れる時期。植物は休眠、地上部は見た目も落ち着きます。とはいえ、完全放置ではなく、次シーズンのための準備を進めておくと安心です。
主な作業リスト
- 防霜・防寒対策(根元マルチング、わら・バークチップ覆い)
- 冬剪定(落葉樹の不要枝や内向枝など)
- 病害虫被害を受けやすい枝の除去
- 枝の整理・切り枝の搬出
- 雪害・強風対策(支え・ワイヤー・ネットなど)
- 道具メンテナンス(剪定ばさみ・鋸・スコップ等の清掃、刃物研ぎ、さび止め)
- 土壌の休ませ・被覆保護
- 来春用に使いたい苗や資材の準備
この時期は大きな植物の成長は止まりますが、見直しと備えの時間と捉え、じっくり準備を進めておくのがよいでしょう。
業界最安値に挑戦〔伐採/剪定/除草〕きしかん園芸
3. 庭の手入れを楽にするコツ
庭の手入れは、やらなければならないことが多く感じられがちですが、習慣と仕組みでずいぶんと負担を軽くできます。以下は「続けられる庭づくり」のためのヒントです。
① 毎日少しずつ手を入れる
大掃除型より「少しずつの積み重ね」が肝心です。毎日10分程度、雑草を抜いたり掃除したりするだけでも、荒れを防げます。大きな手直しが必要になる前に、日々の微調整を心がけましょう。
② 道具・資材をうまく使う
- 除草シート・マルチング:地面を覆っておくことで、雑草の発生を抑制
- 電動芝刈り機・バリカン:手動では体力的にきつい芝刈り作業をスピードアップ
- 刃物研ぎ器・スプレーボトル・薬剤調合器具:道具を整備・適切に使えば作業効率が跳ね上がります
- 折りたたみ式バケツ・ガーデンワゴン:刈った枝や落ち葉を一時的に置く道具があると、移動の手間が減ります
道具を準備しておくだけで、雑な手入れにならず、疲れにくくなります。
③ メンテナンスが楽な植物選び
手間を減らしたいなら、そもそも「世話がかかりづらい植物」を選ぶことも戦略です。
- 庭木(低メンテナンス):キンモクセイ、サザンカ、オリーブ、シマトネリコ、ナツハゼなど
- 花:マリーゴールド、パンジー、ゼラニウム、ペチュニアなど、耐暑性・耐寒性のあるもの
- グランドカバー:シロツメクサ、リシマキア、クリーピングタイム、タマリュウなど
- 多年草・宿根草:一度植えれば毎年出てくる(種類選びは重要)
ただし、どの植物も完全無手間ではありません。定期チェックと最低限のケアは必ず行いましょう。
④ レイアウト・設計で負荷を抑える
庭そのものの構造を工夫して、手入れをしやすい形にしておくことも大切です。
- ゾーニング:高木、低木、草花・グランドカバーを層構成的に配置し、管理エリアを整理
- 通路・マルチスペース設置:管理しやすい動線を確保
- 景観を兼ねたマルチング材・敷石利用:見た目を維持しつつ、土のむき出しを減らす
- 水場・散水設備設計:スプリンクラーやタイマー式ホースを導入し、水やりを自動化
こうした構造段階での配慮が、日常管理の手間を大きく軽減してくれます。
⑤ プロへの部分依頼を賢く活用
自分でできることが限られてきたら、部分的にプロサービスを使うのも賢い選択です。
例えば、「大きな樹木の剪定」「大量の枝葉の処理」「芝生の全面メンテナンス」など、重労働や安全性が伴う作業をプロに任せることで、自分の作業負荷を抑えつつ庭を保てます。
実際、小田急くらしサポートでは、「庭木の剪定・植栽管理」「芝刈り」「草刈り」「枝葉の撤去」などをメニュー化しており、必要な作業だけ依頼できる形式です。
見積もりを取るだけ取ってみて、見比べるのも大事な検討です。
⑥ 見える化で管理をルーティン化する
- 記録・チェック表を作る
「今月何をしたか」「次はいつ何をするか」をノートやスプレッドシートで管理すると、抜け・忘れが減ります。 - 月次・四半期チェックリスト
たとえば、3月:枯葉清掃・土壌改良、6月:害虫チェック、9月:剪定準備、12月:冬支度、など。 - 目に見える区画分け
花壇・芝生の区画を明確にし、作業対象を限定できるようにしておくと、手入れ範囲が把握しやすくなります。
4. プロ活用のメリットとコスト感
庭の手入れをすべて自分でやるのは体力・時間的に限界があります。プロに一部または全面的に頼むことで、安心感や見栄えの向上を得られます。以下は、そのメリットと相場感、および注意点です。
業界最安値に挑戦〔伐採/剪定/除草〕きしかん園芸プロに頼むメリット
- 仕上がりの美しさ
専門的な剪定技術により、樹形が整い、見た目が格段に良くなります。素人が切ると不格好になったり、切りすぎたり少なすぎたりしがちです。 - 枝葉・ゴミ処理まで任せられる
剪定後の枝葉処理は意外と手間がかかりますが、プロに頼めばその部分も包含して対応してくれることが多いです。 - 手間・労力の削減
重労働や危険な高所作業を安全に任せられます。体力的・時間的コストを抑えられます。 - 道具を持たなくてもいい
高性能な道具や機材を自分で揃える必要がなく、手元にある基本的な道具だけで維持作業に専念できます。 - 安心感・保証
契約や見積もりをしっかり行い、アフター対応を組み込む業者なら、仕上がりや後片付けも安心です。
プロ利用の相場感(参考)
作業内容や樹高、庭の広さ、立地条件、ゴミ量などによって費用は大きく変わりますが、小田急くらしサポートの例も参考になります。
| 項目 | 相場(目安) |
|---|---|
| 低木(〜1.5m程度)剪定 | 3,000〜5,000円/本程度 |
| 中木(2〜3m) | 4,000〜7,000円/本 |
| 高木(3〜5m) | 8,000〜15,000円/本以上 |
| 芝刈り | 300〜600円/㎡程度 |
| 草刈り | 数百円/㎡前後 |
| 処分費用 | 剪定金額の20%程度を加算する例あり |
| 基本料金 / 出張料 | 業者によって別設定あり |
注意として、見積もり時には下記点を確認しておくとよいでしょう。
- 料金に枝葉処理・運搬費・ゴミ処理費が含まれているか
- 高所作業、足場設置、重機使用などの追加料金の有無
- 作業保証・アフター対応があるか
- 料金体系(日当制、時間制、単価制など)
- 利用時期(オフシーズンだと割引あり)
- 複数業者からの比較見積もりを取る
プロに頼むことを「手抜き」だと感じる必要はありません。適材適所で任せることで、自分の時間と体力を温存しつつ庭を整えていくことが、長く庭と付き合っていく秘訣です。
5. ワンランク上の庭づくり:応用テクニックと視点
庭を「美しいだけでなく、心地よい場所」に昇華させるための応用テクニックをいくつかご紹介します。
グランドカバー・地被植物の層構成を意識する
グランドカバーを大胆に使うと、土むき出し部分が少なくなり、雑草抑制にも寄与します。さらに、低い植物・中間草本・小低木というように層状につくると、見た目に深みが出ます。
コンパニオンプランツ(混植)による自然防除
ハーブや香りのある植物を樹木・草花の間に植えると、害虫忌避効果を狙えます。例えば、バジル、タイム、ラベンダー、ニンニクなど。また、花粉媒介者や天敵を引き寄せる植物も相性がよいです。
水景や小物要素の導入
- 水鉢・小型噴水:水の音が心地よさをプラス。植栽との相性を考慮して配置を。
- 石・岩・立石:和風庭園風にアクセントを。周囲の緑と調和するよう配置する。
- 照明:夜間照明を工夫すると、庭が“昼と夜で違う顔を持つ空間”になります。
- 通路やステップ石:庭を歩きやすくしつつ、視線誘導・鑑賞の演出にも。
季節感を意識した植栽構成
庭に四季のリズムを感じられるよう、花や葉の変化、紅葉、実のなる木、常緑樹を組み合わせておくと、1年を通じて庭を楽しめます。
ミニマル化・省スペース庭づくり
都市住まいや狭い庭なら、鉢植えやコンテナガーデン、壁面緑化、垂直植栽などで「緑を楽しむ」形式にするのも現実的です。手入れ量は抑えられますが、配置と選種が重要になります。
6. 実体験から学ぶ:よくある悩み・対策と注意点(Q&A形式)
Q1. 剪定したら樹形が崩れて取り返しがつかない
剪定は技術を要します。特に高木や美しい樹形を維持する木では、剪定前の構想が不可欠。枝の切りすぎやバランスを崩す切り方をしないよう、剪定前にスマホ写真で角度確認したり、プロの剪定例を参考にするとよいでしょう。
また、剪定後に調整枝を残し、徐々に様子を見ながら切っていく手法も安全です。
Q2. 雑草を取ってもすぐ生えてくる
土中に種子が蓄積されているケースが多く、根絶は難しいですが、以下で抑制できます:
- 毎日の草取りで目立つ発芽を潰す
- 除草シート・マルチングの併用
- 発芽抑制剤や選択除草剤の使用(ただし周囲植物への影響に注意)
- 密植/地被植物で覆うことで、雑草が生える余地を与えない
Q3. 寒さ・霜害で植物が傷む
冬場は根元にマルチング(落ち葉やバーク等)を敷いたり、不織布や寒冷紗で覆うなどで、地表温度の急激な低下を防ぎましょう。さらに、剪定は冬本番前に終えることが望ましいです。
Q4. 虫・病気が頻繁に発生する
- 日頃から風通し、間引き剪定、下枝除去などで湿気を下げる
- 定期的な薬剤散布(有機JAS対応物、木酢液、石鹸水、展着剤使用など)
- 病斑枝は早めに切り取り、焼却または袋詰めで処分
- 健康な土づくり(微生物豊富な土壌)は、植物自身の抵抗力を高めます
Q5. 作業がきつくて続かない
- 作業範囲を「小区画」に区切り、毎日少しずつ進める
- 重い作業は複数日に分けて行う
- 道具を厳選・整備して作業効率を上げる
- 高所樹木や大掛かりな作業はプロへ任せ、自己作業を軽くする
7. 庭づくりへの提案:あなたの庭を育てるステップ・シナリオ
庭を「作る」という視点で、初心者〜中級者を前提にしたステップ案を提案します。これをガイドラインに、あなたの庭の性質や好みに合わせてアレンジしてみてください。
ステップ 1:現状把握・目標設定
- 現在の庭の状態を写真で記録
- 「どんな庭にしたいか」のイメージを固める(雑木風、和風、洋風、ナチュラルガーデン、草花重視など)
- 面積・日当たり・土質・傾斜・水はけなどを観察
- 管理可能な時間・体力を正しく見積もる
ステップ 2:ゾーニングと基本設計
- 高木・中低木・草花・グランドカバーを配置するゾーンを決める
- 通路・動線を確保し、作業しやすいレイアウトに
- 視線誘導・アクセント構成(石、水鉢、オーナメント、小径など)を入れる
ステップ 3:土壌をリセット・改善
- 表土改良、腐葉土・堆肥投入
- 排水性の改善(砂・軽石混合、ドレイン設計など)
- pH調整(石灰・ピートモス投入など)
ステップ 4:植栽と植え付け
- 樹木・低木をまず配置
- 中下層の草花・宿根草・グランドカバーを植える
- 支柱設置・根付け補助材の活用
- マルチングや敷き材を敷く
ステップ 5:育成期の手入れ・調整
- 雑草管理、剪定、追肥、水やり、病害虫予防
- 成長過程を観察し、不調な株の移植や入れ替え
- 隙間ができたら補植・目土補填
ステップ 6:維持モードへの移行
- 記録・チェック表の運用
- 年次・月次スケジュール管理
- 必要に応じてプロ依頼(剪定・芝全面手入れ・大物処理)
- 植物のリニューアル・更新を定期的に
このようなステップを踏むと、庭は「育てながら整える場所」へと進化していきます。
8. まとめ:理想の庭を日々育むために
庭の手入れは、一度にすべてをやろうとすると負荷が大きくなりがちですが、
以下のポイントを押さえて継続すれば、確実に美しい庭を維持できます。
- 雑草除去、剪定、土壌改良、花壇・芝の管理を庭手入れの基本フレームとする
- 季節ごとのケアを計画的に回す
- 毎日の少量作業、道具活用、植物選定、設計段階の工夫で手間を減らす
- プロ依頼も視野に入れ、部分的に使うことでコスト・労力を最適化
- 植物・レイアウト・応用技術を取り入れて、庭を「暮らしの風景」に昇華させる
「庭をきれいにしたい」と思った今こそが、始めどきです。少しずつ、計画的に手を入れていけば、あなたの庭はあなた自身の手で、年月とともに「風景」になっていくでしょう。