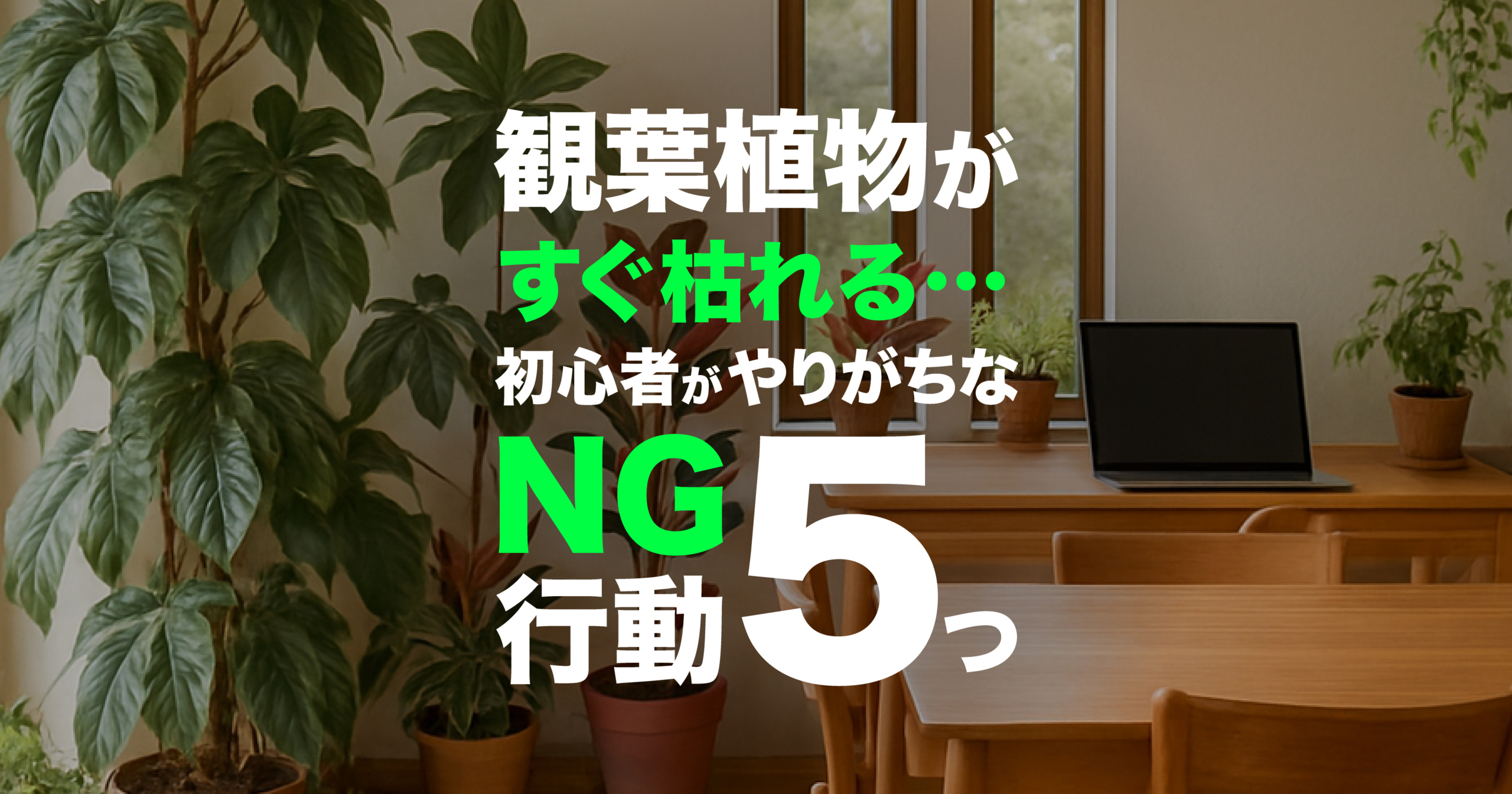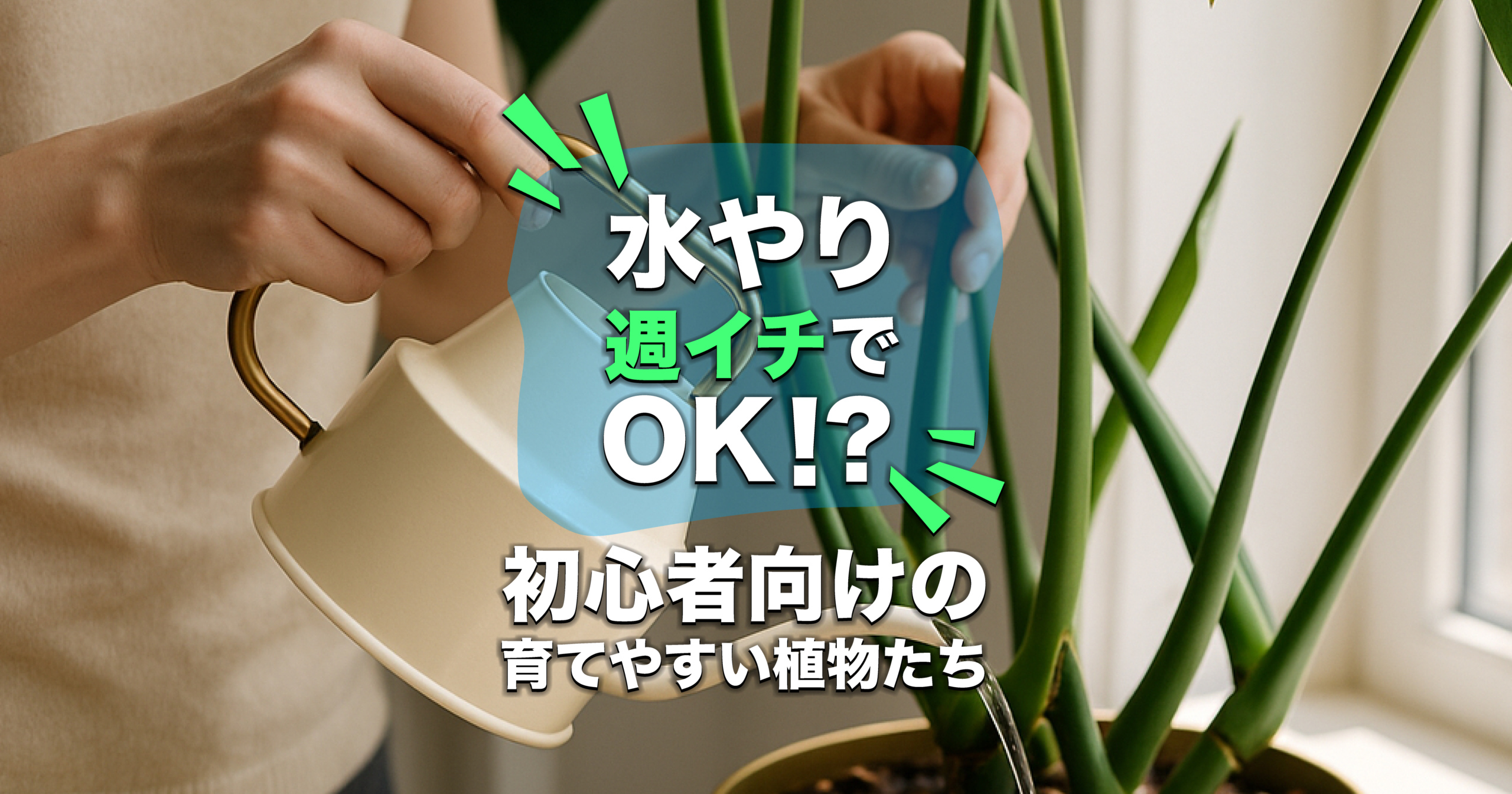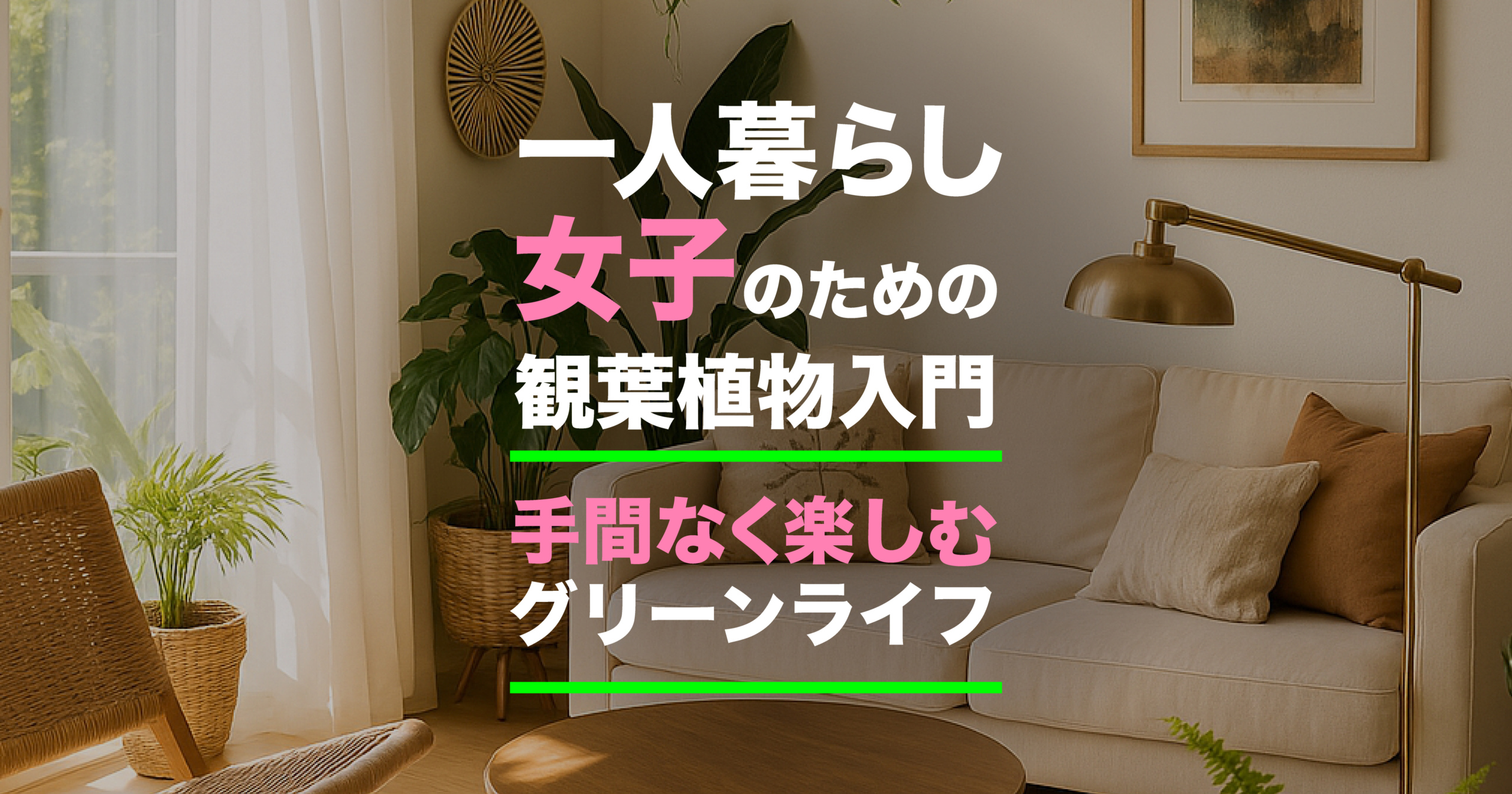こんにちは!
お部屋の雰囲気を一気に垢抜けさせてくれる観葉植物。
インテリアとしても人気ですが、「買ってみたけどすぐ枯れてしまった」「どうしてもうまく育てられない」
という声も多く聞かれます。当然私も、最初の方は全く植物が元気に育たなかったり、時には枯らしてしまったり、うまくいかない日々が続いてました・・。
実は、ちょっとしたキッカケとそのバランスが、植物を元気に育てれるコツだったりします!
この記事では、観葉植物が枯れてしまう原因としてよくあるNG行動を5つピックアップし、それぞれの理由と解決策をわかりやすく解説します。これから観葉植物ライフを始めたい方、過去に枯らしてしまった経験がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
1、水をあげすぎる
初心者がもっともやりがちなミスが「水のあげすぎ」です。
枯れてしまう=水が足りないと思い込んで、ついつい毎日水やりをしていませんか?

なぜダメなの?
観葉植物の多くは、根腐れに弱い性質を持っています。土が常に湿った状態が続くと、根が酸素を吸収できず腐ってしまい、最終的には植物全体が枯れてしまうのです。特に、室内で育てている場合は乾きが遅いため、毎日の水やりは逆効果になることも。
水やりの基本は「土が乾いたらたっぷりと」。鉢の表面の土に指を1本入れてみて、第二関節あたりまで乾いていたら水やりのタイミングです。また、鉢底から水が出るまでしっかりあげ、その後はしっかりと水を切りましょう。
2:置き場所が暗すぎる

リビングの隅や玄関など、日が当たらない場所に観葉植物を置いていませんか?インテリア的には映えるかもしれませんが、植物にとっては過酷な環境です。
なぜダメなの?
植物は光合成によって成長します。そのため、光が不足すると葉の色が薄くなったり、成長が止まったりしてしまいます。光が足りない状態が続くと、やがて弱り、枯れてしまうことも。
観葉植物は種類によって必要な光の量が違います。たとえば、サンスベリアやポトスは半日陰でも育ちますが、ゴムの木やモンステラなどはある程度の明るさが必要です。基本的には「レースカーテン越しの日差しが入る明るい窓辺」がベストポジション。直射日光は避けつつ、できるだけ自然光が届く場所に置きましょう。
3:風通しが悪い場所に置く

「植物だから室内でも大丈夫」と思いがちですが、風通しも植物にとって大切な要素です。
なぜダメなの?
空気が流れないと、土の中の水分が蒸発しにくくなり、根腐れの原因になります。また、カビや害虫が発生しやすくなるリスクも。植物にとっては“蒸れ”が大敵なのです。
定期的に窓を開けて換気をしたり、サーキュレーターを使ってやさしく空気を循環させたりすると、植物にとって快適な環境になります。特に梅雨時期や湿度の高い季節には意識して風を通してあげると◎。
4:肥料を与えすぎる/与えなさすぎる
「早く大きく育ってほしい」と願うあまり、肥料をたっぷり与えていませんか?または、「肥料って必要なの?」とまったく与えていないケースも意外と多いです。

なぜダメなの?
肥料の与えすぎは「肥料焼け」を引き起こし、根にダメージを与えてしまいます。一方、与えなさすぎると植物に必要な栄養が不足し、成長が止まってしまいます。
肥料は「適切なタイミングと量」で与えることが大切です。基本的には春から秋の生育期に、月1回程度の緩効性肥料、もしくは2週間に1回程度の液体肥料を与えると良いでしょう。冬は休眠期なので、肥料は不要です。説明書に記載されている使用量を守ることがポイントです。
5:植え替えをしない
買ったままの状態で何年も同じ鉢に入れっぱなし…そんな方も多いのではないでしょうか?
なぜダメなの?
植物は成長するにつれて根が張り、鉢の中が窮屈になっていきます。すると、根詰まりを起こして水や栄養をうまく吸収できなくなり、枯れてしまう原因になります。また、古くなった土は栄養が少なく、水はけも悪くなります。
一般的には1〜2年に一度、ひと回り大きな鉢に植え替えるのが理想です。植え替えのベストタイミングは、春〜初夏の成長期。新しい土を使って根を軽く整理しながら、リフレッシュさせてあげましょう。根の様子を見て、黒くなっていたり腐っている部分があれば、清潔なハサミでカットしておくと安心です。
まとめ:NGを避けて、植物との暮らしを楽しもう
観葉植物は「手間がかかりそう」と思われがちですが、ポイントを押さえれば意外とシンプル。
むしろコツを掴むと一気にハマる魅力があります!
今回ご紹介した5つのNG行動を避けるだけでも、観葉植物の寿命はぐっと伸びます。
自分のライフスタイルに合った種類を選び、無理なく育てられる環境を整えることで、緑との暮らしはもっと楽しくなりますよ!
「枯らしてしまったのも勉強!」と前向きに捉えて、ぜひもう一度チャレンジしてみてください!!